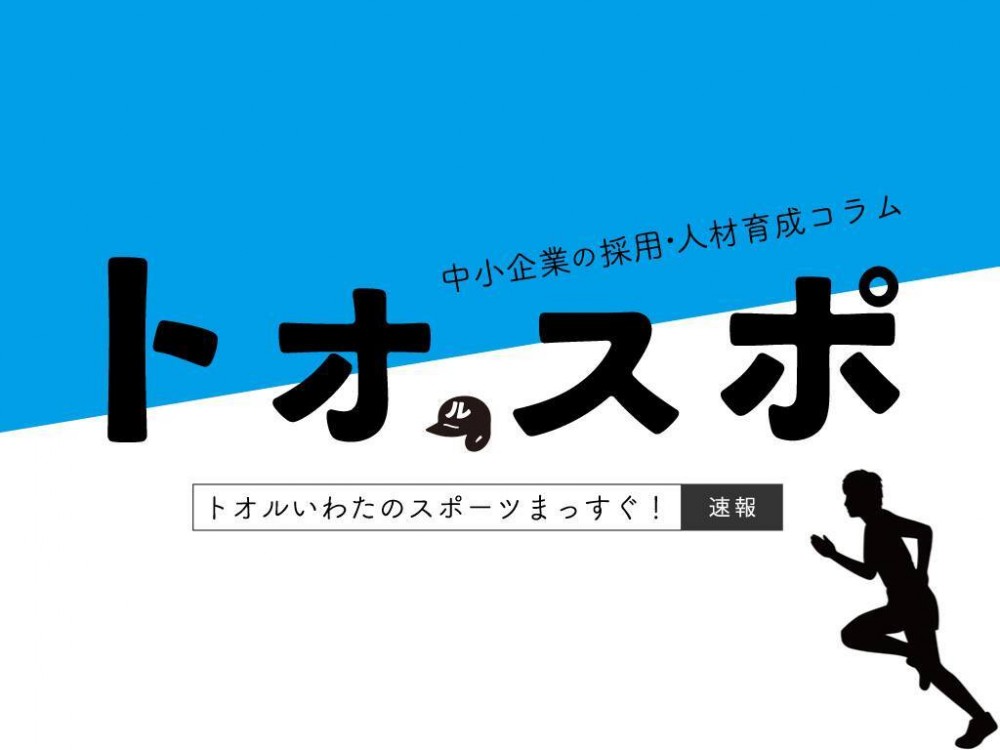2025年5月13日に配信されたニュースから引用します。
「フェンシングの全国高校総合体育大会(インターハイ)岐阜県予選で、
同じ高校の選手が対戦して一方の選手が故意に負けたとして、
再試合が実施されることが13日、県高校体育連盟フェンシング専門部への取材で分かった。
インターハイ出場権を得るため、勝った選手の関係者が敗れた選手に負けるように頼んだという。」
高校年代の最大の目標となるであろうインターハイ。
その県予選でのこと。
6人が総当たりで戦い、成績上位2名がインターハイ出場権を得る仕組み。
それまで4戦全勝だった選手と2勝2敗だった同じ高校の選手が最終戦で戦うことに。
4戦全勝だった選手は最終戦を前に出場権を獲得。
一方の選手は最終戦に勝てば出場権を得られるというシチュエーション。
3年間苦楽をともにしてきた同じ高校の仲間同士の対戦。
そこで関係者(おそらく指導者だと思いますが)から、
すでに出場権を得ている選手に負けるように指示があったとのこと。
指示通りの結果となり、4勝1敗の選手と3勝2敗の選手が上位2名となり、
同じ高校の2名がインターハイ出場権を得た形となりました。
しかし意図的に勝敗が決したことを問題視した連盟が再試合を決定。
後日、再試合となる模様です。
個人種目ではありますが、同じ高校の部活動の中まであればチームスポーツでもあります。
インターハイへの出場経験は、その後の大学へのスポーツ推薦の条件にも含まれる可能性もあります。
県大会敗退とインターハイ出場では経歴も変わりますね。
他のスポーツでも近しい事象は起こっているかと思います。
サッカーのワールドカップでも日本チームが後半15分ほどボール回しに終始し、
得点を取りに行かなかったこともありました。
プロ野球でも、自チームの選手にタイトルを取らせるために、
タイトル争いをしている相手に対し意図的に勝負を避けたりします。
今回の再試合、4戦全勝の選手が一番やりづらいと思います。
2勝2敗の選手は本気で勝ちにいくだけですが、
全勝の選手はチームメイトとどう戦うのか。
仮に真剣に戦って負けたとしても私であれば周囲の反応が気になります。
わざと負けたのではないか?という疑念を持たれかねません。
勝ったとしたら仲間の夢を奪うことになるかもしれません。
皆様がこの学校の指導者であったなら、どういう指示を出しますか?
こういう状況での判断、決断が、経営者や管理職において非常に重要だと思います。
人としての判断基準を部下は見ています。
またそれが自社、自組織の判断基準となり人が育ちます。
一見会社経営には関係のないフェンシングの話題ではありますが、
社内で判断基準のすり合わせをしてみると良いかもしれませんね。