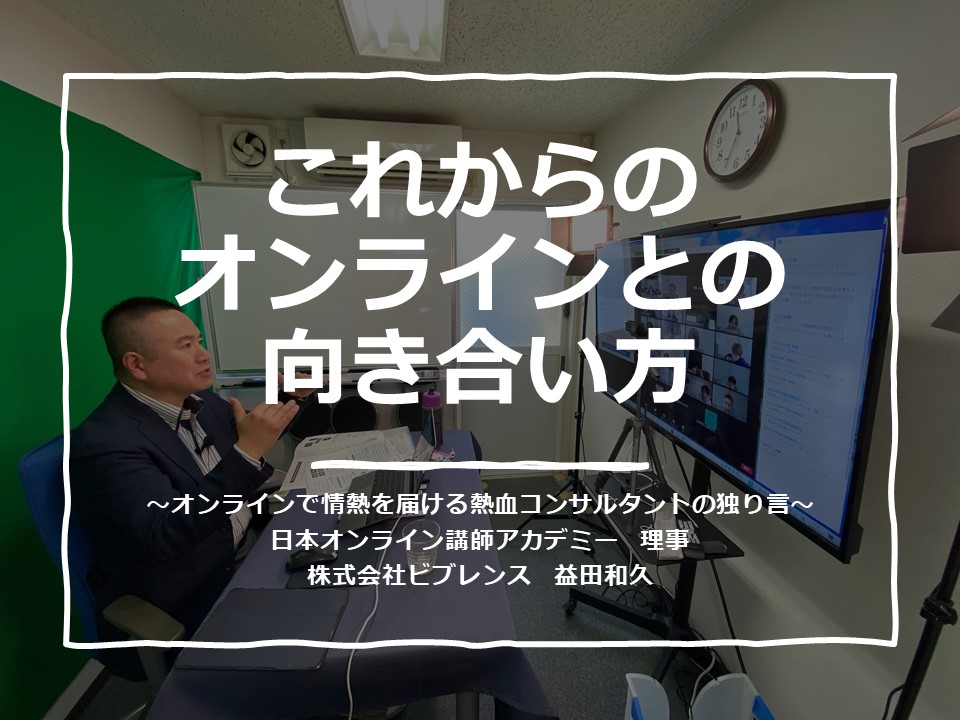日経新聞に、エール大学の心理学者ブライアン・ショル氏のエピソードが紹介されていました。
コロナ禍のZoom会議中、いつもは意見が合う同僚の発言に違和感を覚え、逆に普段は意見が異なる同僚の主張に深く共感したそうです。
後で振り返ると、前者は古いノートパソコンの内蔵マイク、後者はプロ級のホームレコーディングスタジオから参加していたとのこと。
彼の直感は正しかったのです。
米国科学アカデミー紀要に発表された研究では、音声の質が悪いと、内容が同じでも聞き手は話し手を否定的に評価することが明らかになりました。
声を生業にしている私にとって、この記事は非常に気になるものでした。
なぜなら、オンラインでは対面とは異なり、声の聞こえ方が大きく変わることを、日々実感しているからです。
弊社のオンラインサポート全般を担当しているT氏は、研修の配信前に音声や映像の品質テストを何度も繰り返します。
時には「このカメラに変えてみてください」「マイクをこちらに交換してください」といったリクエストもあります。
正直なところ、「そんなに違うものかな」と思うこともありました。
しかし、今回の研究結果を読んで、やはり大きく違うのだと再認識しました。
この研究では、5100人を超える被験者が、同じ内容を話す録音を聞きました。
音声の質が悪いと、求職者としての適性、デート相手としての魅力、事故説明の信頼性、知性のすべてにおいて、一貫して低く評価されたそうです。
つまり、あなたがどれほど素晴らしい内容を話していても、音声が不快であれば、その価値は大きく損なわれてしまうということです。
弊社は研修で「通る声、伝わる声」の出し方を指導しています。
少し高めの声で話すこと、語頭と語尾をハッキリと発音すること、キーワードはゆっくりと繰り返し、その前後に間を取ること。
これらは電話応対やオンラインセールスにおいて、非常に効果的なテクニックです。
しかし、今回の記事を読んで、それだけでは不十分だと痛感しました。
声の出し方という「ソフト」の部分をいくら磨いても、マイクという「ハード」が貧弱であれば、その努力は十分に伝わりません。
逆に言えば、良質なマイクとカメラがあれば、私たちの声の魅力は何倍にも増幅されるのです。
弊社では、カメラはロジクールの上位モデル、マイクはオーディオテクニカのFMラジオなどで使用されているレベルのものを使用しています。
最初は「そこまで必要か」と思いましたが、実際に使ってみると、その差は歴然でした。
声の輪郭がクリアになり、抑揚が豊かに伝わり、何より聞き手が疲れません。
長時間の研修やミーティングでは、この「疲れない」という要素が極めて重要なのです。
ショル氏は「オンライン上で自分の声が他人にどのように聞こえているかを絶対に調べるべきだ。そして、よい感じに聞こえていないのであれば、何らかの改善策を講じよう」と述べています。
まったく同感です。
オンラインコミュニケーションが日常化した今、ツールへの投資は不可欠です。
私たちの専門性や信頼性、そして説得力を担保するための必要経費です。
ノートパソコンの内蔵マイクで重要なプレゼンテーションに臨むことは、しわくちゃのスーツで商談に行くようなものかもしれません。
オンライン経由でコンサルやセールス、またマネジメントをする機会のある方は、自身のアイデアや専門知識を最大限に伝えるために、ご自身の価値を正当に評価してもらうために。
今一度「オンラインでの音声環境」を見直す価値はあると思います。
何でもそうですが、ビジネスツールにはそれなりのお金をかけないといけないのだなと再認識した今日この頃です。