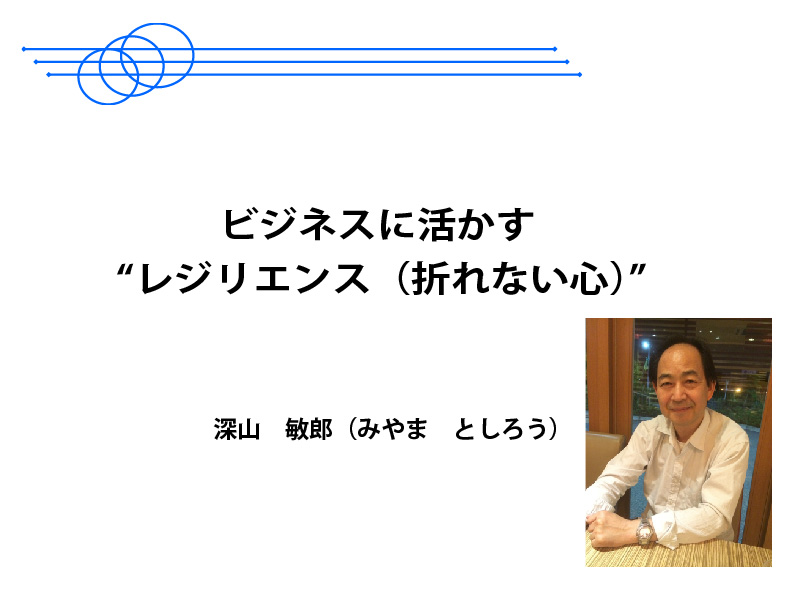第37回 シェイクスピアの登場人物のレジリエンス(25)ヘンリーVI第一部
2022/03/01
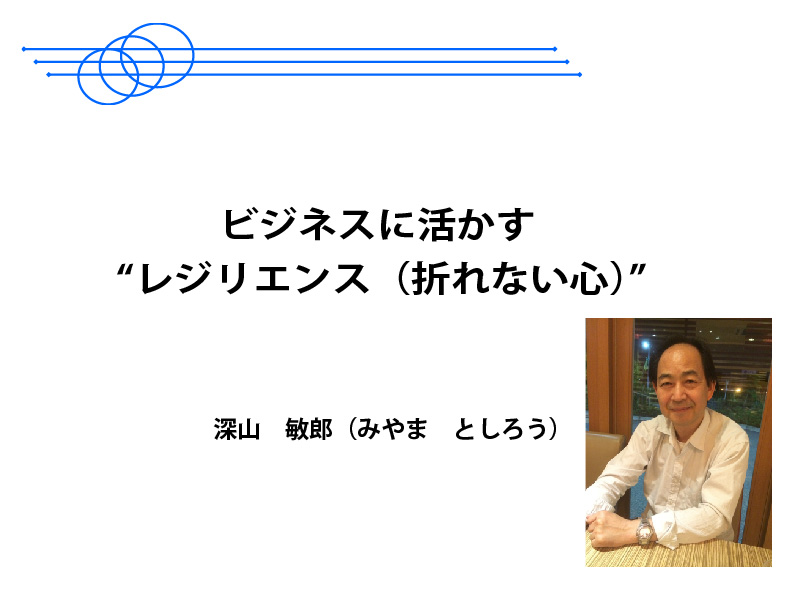
前回はシェイクスピアの問題劇「コリオレイナス」の主人公、コリオレイナスのレジリエンスについて検討してみました。
今回はシェイクスピア作品の中でも最も初期に書かれたいわば“デビュー作”と言われている「ヘンリーVI(三部作)」(1590-1592)の第一部の主人公の一人、トールボット卿(後のシュルーズベリー伯爵)のレジリエンスを検討してみます。
この作品にはさまざまな主人公級の登場人物が現れるのですが、第一部の中で筆者がもっとも興味を持った人物は、トールボット卿です。
恐らく当時の個性あふれる名優がこの役柄を演じたものと思われます。
「ヘンリーVI三部作」は英仏百年戦争時代の英雄の乱立劇
「ヘンリーVI」は上述のように1590年~1592年頃に書かれたシェイクスピアの記念すべきデビュー作と考えられています。
当時は三部作ではなく、現存する「ヘンリーVI第二部及び第三部」が二本連続で上演された戯曲であっただろうと言われています。
その後、シェイクスピアが第一部を書き足したというのが大方の説になっています。
第二部と第三部にあたる部分(別名で上演)はシェイクスピアが26歳頃に書かれたと言われています。
いわば戯曲作家として若造であり、恐らく他の作家との共同作品であったであろうと推察されていますが、明確な証拠があるわけではありません。
総合的に判断すると、第二部、第三部は共同著作であり、第一部は後からシェイクスピアが独自に書き足して三部作にしたというのが自然です。
当時は著作権の概念は今ほど厳密なものではなかったことから、十分に考え得ることです。
この作品の背景には、参照された当時の歴史書として、エドワード・ホールの歴史年代記「ランカスター、ヨーク両名家の和合」(1548)やラファエル・ホリンシェッドの「イングランド、スコットランド、アイルランドの年代記」(初版1548)の増補版(1577)だと考えられています。
しかし、シェイクスピアのこの戯曲が史実を忠実に再現しているかと言われれば、そうではない部分が多々見受けられます。
劇として面白くするために年代を逆にするとか、人物を創り出してしまうなど、かなりいろいろな細工をしているということが、さまざまな研究で分かってきています。
ここでは詳細は省略致します。
私は残念ながらこの芝居そのものを舞台で観たことがなく、RSC(ロイヤルシェイクスピアカンパニー)の日本公演「The Hollow Crown」の中に部分的に物語が出てきたという程度の記憶です。
BBCのDVDでは、トールボット卿は名優トレバー・ピーコックが演じており、配役の中でも冒頭に記述されています。
また、グロスター公爵をデーヴィッド・バークが演じています。
バークは、有名なTVシリーズ「シャーロックホームズ」の前半でドクター・ワトソンを演じています。
後半ライヘンバッハの滝からホームズが帰還してからのワトソンはバークの親友であり、私の友人のエドワード・ハードヴィック(「80日間世界一周」などで有名なサー・セドリック・ハードヴィックの息子で数々の映画、TV、舞台で活躍)が演じたことは既にこのコラムシリーズでも書いたと記憶しています。
私生活は陽気な人で、日本に来た時にすぐに仲良くなりました。
また、日本での上演にあたって私にいくつかアドバイス(例えば、日本ではお金が欲しいというのはどういうジェスチャーになるのか?といったこと)を求めてきて、すぐに舞台に取り入れていました。
私の知る英国の舞台人に共通しているのは、こうしたオープンさと柔軟性です。
少し寄り道の話になりました。
トールボット卿とジャンヌ・ダルクらの対立が見せ場
「ヘンリーVI」第一部では、トールボット卿とオルレアンにおけるフランス軍のジャンヌ・ダルクの対立が大きな見せ場になっています。
ジャンヌ・ダルクはフランス軍のヒロインとして描かれているかというと、そうではなくこの芝居の中ではフランスの魔女のような扱いです。
また、トールボット卿とフランスのオーヴェルニュ伯爵夫人との衝撃的な対面や騙しあいも、舞台を盛り上げています。
「ヘンリーVI 第一部」のストーリー
舞台はヘンリーV(ヘンリーIVにおいて「ハル王子」として登場)の葬式からスタートします。
ヘンリーVは名君であったといわれていますが、ヘンリーVIは生後9か月と幼く、国を治める能力がありません。
王の叔父グロスター公爵と大叔父ウィンチェスターの司教ヘンリー・ボーフォートとの反目があり、これが原因となってイギリス軍はフランスとの闘いで苦戦しています。
結果として勇猛果敢なトールボット卿は敵地で孤軍奮闘をすることになります。
フランスのシャルル皇太子(後のフランス国王シャルル七世)もイギリスの許可を得ずに戴冠式を行います。
トールボット卿の率いる軍とジャンヌ・ダルクの率いる軍とが激しく戦い、一進一退の状況です。
シェイクスピアは、ジャンヌ・ダルクを悪魔の霊力を借りた女として描きます。
ロンドンでは謀反を起こした血縁のリチャード・プランタジェネット(後のヨーク公爵)が貴族たちに嫌味を言われており、父の汚名や死の真相を知るために監獄に伯父モーティマー伯爵を訪ねます。
彼はホットスパーらとともに国王ヘンリーに対して不満を持ち、結果として謀反を起こしたのです。
伯父の説明は、リチャード・プランタジェネットや伯父のモーティマーの一族は、王座に就くことの出来る立場でありながらヘンリーVに邪魔をされて不遇に陥ったと知ります。
司教派とグロスター公爵派との権力闘争が激化して、部下たちも小競り合いをします。
ヘンリーVIはプランタジェネット家の復権を許し、リチャード・プランタジェネットはヨーク公爵に任命されます。
フランスでは、ジャンヌ・ダルク軍が勢いづきます。
パリでヘンリーVIの戴冠式が執り行われることになります。
ランカスター家とヨーク家の間の薔薇戦争も萌芽が見受けられます。
因みに薔薇戦争は英仏100年戦争の敗戦責任の押し付け合いと言われています。
トールボット卿と息子ジョン・トールボットはフランスで命を削りながら戦っているのですが、援軍がなく、二人とも犠牲になります。
ウィンチェスター司教は、ローマ法王から枢機卿の地位を与えられます。
そして国を奪い取ることを画策します。
プランタジェネット家のヨーク公爵の攻勢でフランスは敗北します。
ジャンヌ・ダルクは捕らえられて、魔女であると考えられて火あぶりになります。
サフォーク伯爵は、貴族の娘を王妃候補として推薦します。
そして結婚が決まります。
一方、フランスのシャルルと和平が結ばれて、シャルルが副国王になって芝居は終わります。
トールボット卿のレジリエンス
彼のレジリエンスは、以下のようになりました。
今回も以下の代表的なレジリエンス要素を用いて分析をします。
1.自己効力感
2.感情のコントロール
3.思い込みへの気づき
4.楽観
5.新しいことへのチャレンジ
自己効力感は非常に高く、それは彼の将軍としての自信と伯爵として国家を愛するプライドに裏付けられています。
それは彼の数々の美しいスピーチに表れています。
国を愛し、身内を愛する気持ちがふんだんに表現されています。
あくまでもシェイクスピアの創作ではありますが。
感情のコントロールは、ある程度以上、うまく出来ていたと考えられます。
敵であるオーヴェルニュ伯爵夫人に招待された時に、表面上は女性の色気目当てに出向くように振舞うのですが、実際のところは敵の意図を予見した上で見事に裏をかきます。
思い込みへの気づきという面では、上記のように非常に柔軟に、そして戦略的に振舞います。
楽観という面は、優秀な将軍として活躍を続けていたところから楽観はなかったと思われます。
また、息子ジョンが自分を支援に来た時に、戦況が最悪であるために逃がそうとします。
せめて自分の血統が絶えないようにと伝えますが、実はそれ以上に息子への愛情からです。
因みに勇敢な息子も親を助けようとします。
新しいことへのチャレンジという視点は、いろいろなチャレンジを続けていると考えられます。
上記オーヴェルニュ伯爵夫人への対応など、味方を門外に待たせておいて自分が窮地に陥ると合図をして、大砲で門を破らせます。
次回は、シェイクスピアの歴史劇「ヘンリーVI三部作の内、第二部」を検討してみます。
レジリエンスの高い人の特徴を詳しく知りたい方は、拙著:「レジリエンス(折れない心)の具体的な高め方 個人・チーム・組織」(セルバ出版)などをご覧いただければ幸いです。
また、シェイクスピアに関するビジネス活用のご参考として、拙著:「できるリーダーはなぜ「リア王」にハマるのか」(青春出版)があります。
この書籍はシェイクスピア作品を通してビジネスの現場にどう活かしていくかを検討するために書かれました。
toshiro@miyamacg.com (筆者:深山 敏郎)
株式会社ミヤマコンサルティンググループ