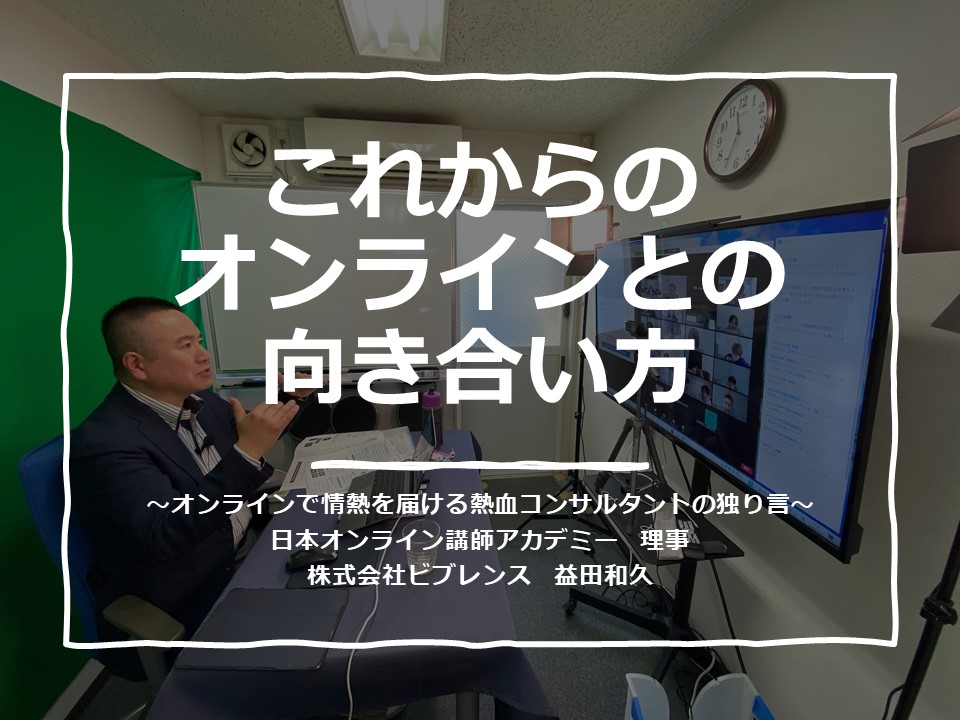日本経済新聞に、法人向けeラーニングでAIの活用が広がっているという記事が掲載されました。
社員教育を生業にしている私にとっては、見逃せない内容です。
グロービスは講義内容を逐次質問できるAIパートナーを導入し、ヒューマンホールディングスは目標を定めて個別の64種類の対策を示すAIマンダラチャートを開発したとのこと。
リスキリング需要が高まる中、各社がAIによる個別指導で学習効果を高めようとしています。
グロービスの学び放題を活用している話はよく聞きますし、内容も充実していてコスパもいいと思います。
費用負担は会社によって違いますが、このくらいの自己投資ツールが手元にあるというのは、スキルアップという点では大変ありがたいはずです。
確かに集合研修はそれなりのコストもかかりますし、人を集めて長時間拘束するのも大変です。
だからこそ、各々の都合で学習できるeラーニングに需要があるのもよくわかります。
記事によると、産業能率大学総合研究所の調査では、企業内で使っている教育手段として「eラーニング」が75%と最多で、2019年比18ポイント増加したそうです。
一方、「外部講師による集合研修」は同11ポイント減の71%でした。
矢野経済研究所によると、2025年度の法人向けeラーニング市場は前年度比5%増の1299億円の見込みとのこと。
コロナ禍を追い風に、確実に市場は成長しています。
eラーニング側も、ただ動画を流すだけでは飽きられるとわかっています。
だからこそ、AI機能を搭載するなど、いろんな工夫を加えているのでしょう。
コンテンツによっては無料のYouTubeで、作者がわかりやすく解説しているものもありますから、当然の努力なのかもしれません。
それは私たちのような研修会社が、研修手法をブラッシュアップし続けるのと同じです。
グロービスの事業責任者は「ただ動画を見るだけでは飽きられがちで、学びに結びつきづらい」と話しています。
まったくその通りでしょう。
AIとの対話を取り入れることで、単調になりがちなeラーニングのモチベーションを維持する。
試験版の受講者からは「実際の先生より気軽に質問できる」との声もあったそうです。
これは大きな利点だと思います。
一方で、記事は課題も指摘していました。
集合研修は1回あたり数十万円かかり、企業にとって負担は大きい。
eラーニングはコストは低いが、学習者のモチベーション維持や効果が課題だと。
この指摘は非常に重要です。
eラーニングにも集合研修にも、それぞれの良さがあるのです。
実は、eラーニングと集合研修を組み合わせるというのも一つの方法です。
基礎知識はeラーニングで各自が習得し、集合研修では実践的な演習やディスカッション、ケーススタディに集中する。
こうすることで、それぞれの長所を活かすことができます。
弊社でも、事前にeラーニングで理論を学んでいただき、研修当日はロールプレイングや対話に時間を使うという形式を取ることがあります。
記事の最後に「AIが部下の指導を代行することで管理職は時間的・心理的な負担軽減を実感できる」とありました。
確かにそうでしょう。
しかし、これは集合研修も同じです。
外部の専門家に任せることで、上司は教える負担から解放されます。
ただし、ここで注意すべきは、スキルアップとパフォーマンス発揮は別物だということです。
eラーニングやAI、あるいは集合研修によって、部下のスキルは確実に向上するでしょう。
しかし、そのスキルアップした部下を活かすのは、結局のところ上司であり、会社なのです。
いくら知識やスキルを身につけても、それを発揮する場がなければ意味がありません。
学んだことを実践できる環境を整え、チャレンジを促し、失敗を許容する文化を作る。
これは、どんなに優れたAIにも代替できない、上司と会社の役割です。
三菱総合研究所の奥村隆一主席研究員は「従来型の研修だけでは、仕事の現場で活用できるほど内容が定着しない」と指摘しています。
リスキリング投資は費用対効果が低いのが現状だと。
だからこそ、AIを活用した実践的な学習やモチベーション維持にシフトするのだと予測していました。
その通りだと思います。
しかし同時に、実践の場を提供するのは現場であり、上司であることも忘れてはなりません。
研修で学んだことを職場で試し、フィードバックを受け、改善する。
このサイクルがあって初めて、学びは定着し、パフォーマンス向上につながるのです。
結局のところ、eラーニングもAIも集合研修も、すべてはツールです。
それぞれに得意不得意があり、目的に応じて使い分ける必要があります。
コストを重視するならeラーニング、相互作用や実践を重視するなら集合研修、個別最適化を図るならAIの活用。
どれが良い悪いではなく、何を目的とするかによって選択すべきなのです。
人材育成において本当に大切なのは、学ぶ機会を提供することと、学んだことを活かす場を作ること。
その両方が揃って初めて、投資は意味を持ちます。
AIが進化し、eラーニングが充実していく時代だからこそ、人間にしかできない部分、つまり「育てる」という行為の本質を見失わないようにしたいと思う今日この頃です。