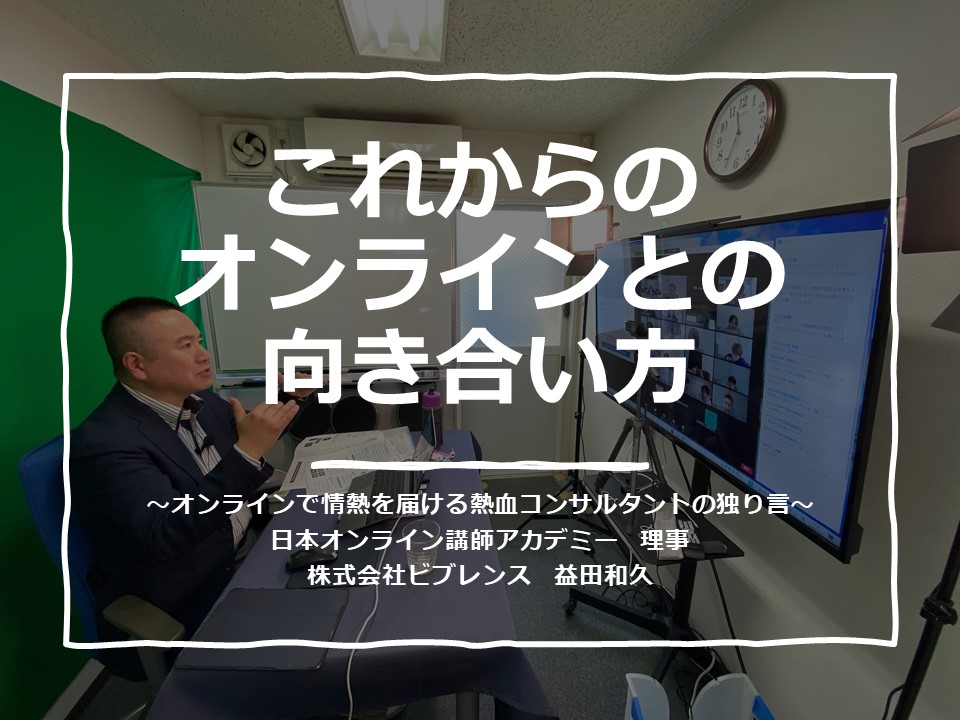愛知県豊明市で全国初となる「スマートフォン等の適正使用の推進に関する条例」が9月22日に可決・成立し、10月1日から施行されました。
この条例は全市民を対象に、仕事や学習以外でのスマホ利用を「1日2時間以内」とする目安を示したもので、罰則はないものの大きな議論を呼んでいます。
堀江貴文氏をはじめ著名人からの批判も相次ぎ、市には賛否両論の意見が多数寄せられているとのこと。
人事教育コンサルタントとして、デジタル技術と人間の関わり方について日々考えている私にとって、この条例は非常に興味深い社会実験だと感じています。
個人的には、スマホ利用制限については「総論賛成、各論反対」のスタンスです。
スマホの過度な利用が子どもたちの睡眠時間や学習時間を削り、家族の会話を減らしている現実は確かに問題でしょう。
実際、モバイル社会研究所の調査によると、学生のインターネット利用時間は1日平均7.8時間にも達しており、これは起きている時間の半分近くを占めています。
文部科学省も、全国学力テストの結果低下の一因として「スマートフォンの長時間利用」を挙げているほどです。
こうした現状を踏まえれば、何らかの対策が必要なことは明らかです。
豊明市の小浮正典市長が条例制定の背景として挙げているのは、不登校対策への取り組みです。
スマホの長時間利用が睡眠不足や生活リズムの乱れを引き起こし、結果的に学校生活に支障をきたすケースが増えているという現場の実感があるのでしょう。
1日2時間という基準についても、青少年の健全な生活を考えれば妥当な線だと思います。
十分な睡眠、学習時間、家族や友人との対面でのコミュニケーション、読書や運動など、バランスの取れた生活を送るためには、スマホ以外に充てるべき時間が必要なのは当然です。
一方で、「IT・DX社会に逆行する」という批判もありますが、これは少し的外れではないでしょうか。
デジタル技術の活用とスマホでの娯楽コンテンツ消費は別物です。
真のDX社会を実現するには、むしろデジタル技術を適切に、合理的に活用できる次世代を育成することが重要でしょう。
スマホ画面を漫然と眺める時間を減らし、その分を創造的な活動や深い思考、人との直接的な交流に充てることができれば、それこそが健全なデジタル社会の実現につながるはずです。
確かに、インテリ層の中には「くだらない」という意見もあるでしょう。
自分たちは良識を備えて適切に対応できるという自信があるのかもしれません。
しかし、世の中全般を見渡せば、デジタルリテラシーや情報リテラシーは思った以上に低いのが現実です。
だからこそ、行政がある程度のガイドラインを示すことには意義があると思います。
豊明市の条例には罰則もなく、あくまで「目安」として市民への啓発メッセージを発しているに過ぎません。
これを機に、各家庭でスマホ利用について話し合うきっかけになれば十分でしょう。
またスマホだけでなく、ネットサーフィンやテレビの長時間視聴も本質的には同じ問題を抱えていると思います。
受動的なコンテンツ消費に時間を奪われ、能動的な活動や学習の機会を失うという構造は変わりません。
豊明市の条例は、そうした問題提起を含んだ包括的な社会提言として評価できるのではないでしょうか。
もちろん課題もあります。
市議会では附帯決議として「市民の自由と多様性の尊重」「誤解を招かない丁寧な説明」「継続的な効果検証と見直し」などが盛り込まれており、運用面での配慮が求められています。
しかし、これからの時代の子どもの教育について、親や学校、そして社会が真剣に向き合うための議論のきっかけとしては、非常に価値のある取り組みだと思います。
DX社会だからこそ、適切で合理的にデジタル技術と向き合える次世代を育成する必要があります。
豊明市の条例は、その社会実験が始まったばかりであることを象徴しています。
完璧な解ではないかもしれませんが、現状に問題意識を持ち、改善に向けて一歩を踏み出した勇気ある取り組みとして、今後の展開を注視していきたいと思う今日この頃です。