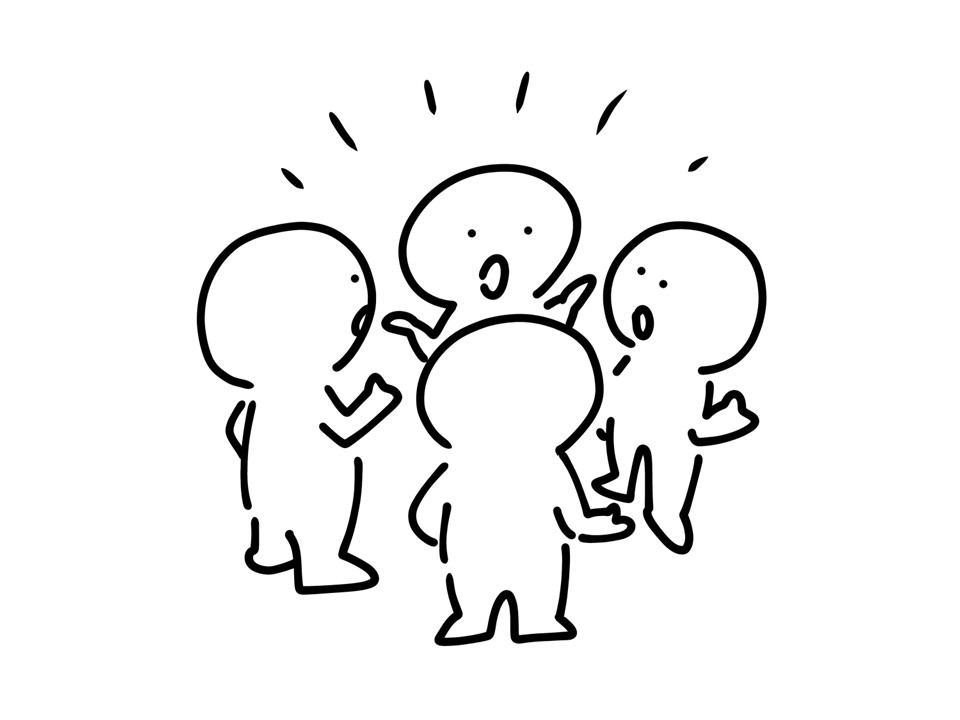井戸端(いどばた)。
井戸端とは、井戸のそばや付近、回り、ほとりなどを意味する言葉です。
江戸時代までは、集合住宅の長屋がありました。
長屋には共同の井戸があり、飲料水や炊事・洗濯などの生活に必要な水を汲んでいました。
複数の人が水を汲みに来るので、他の人が水を汲んでいる時は、待ち時間になります。
そんな時には、雑談に興じていただろうとされていて、世間話や噂話をしている様子を「井戸端会議」と表わされます。
ゲーテの『ファウスト』にも、「地域の人々が生活を共にする井戸があれば人が集い、たわいのない話、そして余計な噂話がはじまった」と描かれています。
SNSや電話といったコミュニケーションツールがなかった時代。
人々は顔を合わせて話をする方法しかありませんでした。
しかし、現代はコミュニケーションツールの多様化もあり、井戸端に集まらなくても雑談などができる環境となりました。
顔を合わせてしていた近所の人との噂話も、相手がいなくても発信することができます。
ドラマなどでよくみるのは、「近所の人たちと近所の人の噂話をしていると、当人が来てそそくさと誤魔化す」なんて場面。
「噂をすれば影がさす」という、ことわざもあります。
身近な人の不確かな話で盛り上がる「暇つぶし」だった「井戸端会議」。
現在は、よく知らない人のことで、よく知らない人たちとの井戸端会議。
いや、井戸端会議というとこより自己発信。
「知っている」
「聞いたこと」
ビジネスでも情報はとても大切です。
情報をどのように集め、どのように使うかが重要になりますね。
私の体験型研修では、その場に起きた「事実」を基に気づきを誘発していきます。