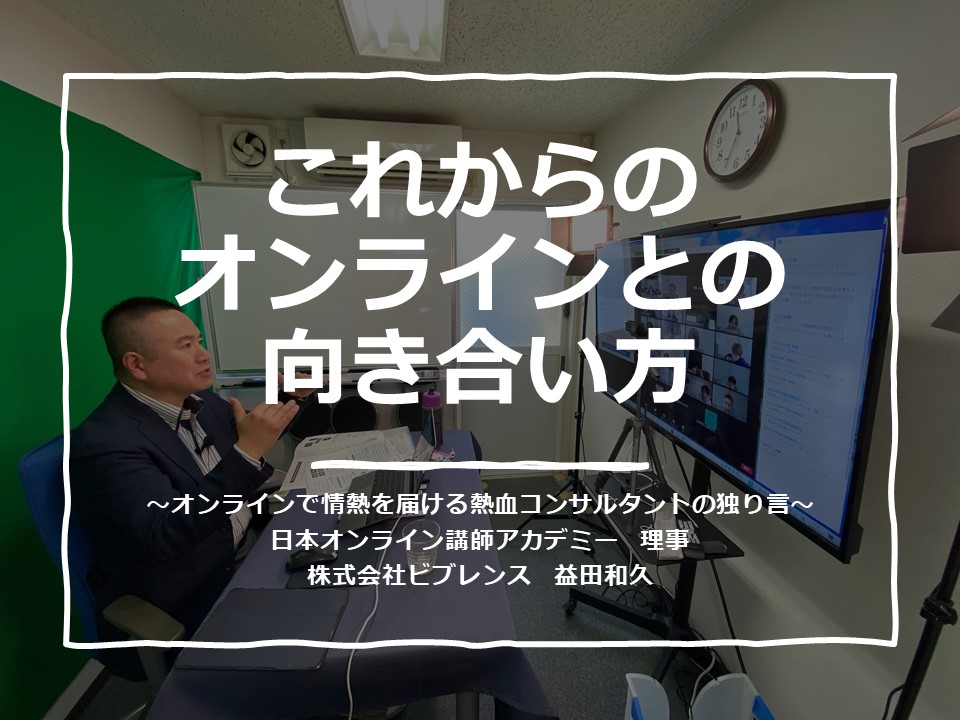先日、日本経済新聞に興味深い記事が掲載されていました。
なんと、日本の自動販売機が急激に減少しているというのです。
2024年の設置台数は204万台で、2013年比約2割減。
このペースだと2050年には半減する可能性があるとか。
自販機といえば、多くの方が飲料の自販機を思い浮かべますよね。
外国人の友人が以前こんなことを言っていました。
「日本は平和で人々の良識がしっかりしている。なぜならお金も商品も入った自動販売機があれだけ街中に置いてあって、ほとんど盗難がないからだ。外国なら一晩でまるまるなくなっている」。
確かに日本だから成り立つ商売なのかもしれません。
実は私、学生時代に自販機の補充アルバイトをしていたんです。
ちょうどカルピスウォーターが発売になった時期で、驚くほど売れた記憶があります。
設置場所によっては1日3回も補充に回ったことも。
この仕事で痛感したのは、補充計画の難しさでした。
売れる本数によって巡回ローテーションが自販機ごとに変わるのですが、これがなかなか難しい。
売れていないのに行くのはムダだし、売り切れで補充が遅れると機会損失になる。
設置場所のお客さんから売り切れの連絡を受けて、何度も呼び出された苦い思い出もあります。
今は売上状況がオンラインで管理できると聞いているので、補充計画も格段に組みやすくなっているはずです。
でも、それでも自販機は減り続けている。
なぜでしょうか?
記事によると、減少の背景には主に2つの要因があります。
一つ目は価格です。
希望小売価格の平均が181.8円なのに対し、スーパーなどの平均価格は102.1円。
約80円もの差があれば、消費者が自販機から離れるのも当然でしょう。
私はここにコンビニが増えたことも影響していると思います。
朝の出勤時にまとめて飲み物を購入する人が増え、会社近くの自販機を利用する機会が減ったのではないでしょうか。
二つ目は「スマホ決済未対応」です。全国の自販機の約6割が現金しか使えないという現実。
キャッシュレス決済が当たり前になった現代において、これは明らかに時代遅れです。
では、自販機に未来はないのでしょうか?
私はそうは思いません。
サントリーが開発した自社自販機専用アプリなどは良い例です。
これは単なる決済手段を超えた、顧客の囲い込み戦略でもあります。
購入傾向の把握、ポイントサービス、ヘビーユーザーへの割引など、様々な展開が可能になります。
さらに踏み込んで考えるなら、売れ行きに応じた柔軟な価格変更も実現できるはずです。
ユニクロが商品を限定してセールを頻繁に実施するのは、緻密な販売戦略に基づいています。
自販機でも同様のアプローチができるのではないでしょうか。
もちろん、自販機のオンライン化には相応のコストがかかります。
通信設備の導入、システム開発、保守管理など、決して安い投資ではありません。
でも人手不足で補充要員の確保が困難になっている現状を考えれば、効率化への投資は避けて通れないでしょう。
この自販機の事例から、私たちが学べることは何でしょうか?
まず、変化への適応の重要性です。
消費者のニーズや技術環境が変わっているのに、従来のやり方に固執していては生き残れません。
自販機業界も、現金決済のみという旧来の仕組みにこだわり続けた結果、競争力を失いつつあります。
次に、データ活用の威力です。
売上状況をリアルタイムで把握できれば、効率的な補充計画が組めます。
これは、あらゆるビジネスにおいて、データに基づく意思決定がいかに重要かを示しています。
最後に、顧客接点のデジタル化です。
アプリを通じた顧客との直接的な関係構築は、単なる商品販売を超えた価値創造につながります。
少しばかり携わった仕事でもあるし、しょっちゅう研修センターや出張先ホテルで利用している私からすると、まだまだ改善の余地があるような気がしてなりません。
「電車の待ち時間など自販機でしか買えない時もある」という需要は確実にあるのですから。
みなさんの職場でも、「なんとなく続けているけれど、もっと良いやり方があるのでは?」という業務があるはずです。
自販機の事例のように、デジタル技術を活用することで劇的に改善できる可能性があります。
大切なのは、現状に満足せず、常に改善の視点を持ち続けること。
そして、新しい技術やツールを恐れずに取り入れる勇気を持つことです。
日本の象徴的な自動販売機が教えてくれる教訓は、意外に深いものがあると感じる今日この頃です。