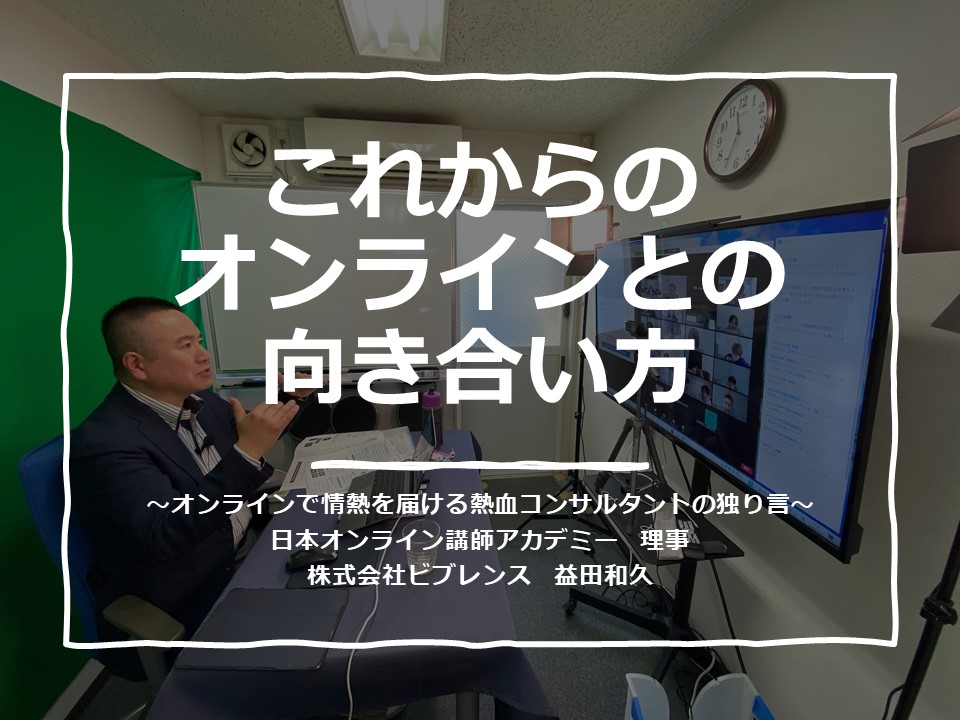前回お話しした「AIとの壁打ち」を実際にやってみていかがでしたか? コラムを読んだお客様から「早速やってみたよ」という声も届いています。
中には「思った以上に使える」「もっと早く始めれば良かった」という感想もいただきました。
一方で、「最初の回答がイマイチだった」「期待していた答えが返ってこない」という声も聞こえてきます。
AIを"便利な相棒"にするには、ちょっとしたコツがあるんです。
今回は、研修でお伝えしている実践的なポイントをご紹介します。
<コツ1:問いを具体化して投げかける>
AIとのやり取りも、人とのコミュニケーションと同じです。
研修でよく聞くのが「人に頼むとき同様、丁寧に且つ具体的に投げかけないと、思った通りのアウトプットは出ない」という声です。
例えば「新人研修について教えて」では抽象的すぎます。
「4月入社の新人10名向けに、ビジネスマナー研修を3時間で実施したい。グループワークも取り入れて、実践的な内容にしたいが、どんな構成が良いか」と具体的に伝えると、格段に精度の高い回答が得られます。
5W2H(いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どのように、いくらで)を意識して質問を組み立てるのがコツです。
実は、いい質問が思いつかない場合の裏技もあります。
ある程度質問を書いた後に「最高の回答を生成するために、必要な情報がありましたら、些細なことでも構いませんので質問してください」と付け加えてみてください。
すると、AIが不足している情報を細かく聞いてきます。
研修でこれをやってもらうと、皆さん「これは使える!」と目を輝かせます。
<コツ2:途中で壁打ちを止めない>
AIの最初の回答で満足してしまう人が多いのですが、それではもったいないです。
「なぜそう思うの?」「他にはどんな方法がある?」「デメリットも教えて」と、どんどん深掘りしていきましょう。
研修参加者からは「自分でもゴールが見えないときは、いっぺんに答えにたどり着こうとせず、手探りしながらいろんな情報を集め、掘り下げていくと、段々見えてくる」という感想をよくいただきます。
一つのスレッドで会話を続けることで、AIがあなたの意図を理解し、より的確な回答をしてくれるようになります。
壁打ちは「継続」がカギを握っています。
<コツ3:AIに構造化・視覚化させる>
複雑な情報を整理したいときは、AIに「見える化」してもらいましょう。
「この情報をロジックツリーにして」「表にまとめて」「時系列で整理して」といった依頼が可能です。
意外と知られていないのが、既存資料の活用です。
「自分でプロンプトしなくても、既に作成してある関連資料を添付すれば読み取ってくれる」という声もよく聞きます。
PDFや画像ファイルも読み込めるAIが増えているので、手持ちの資料を有効活用してみてください。
<注意点:AIとの正しい付き合い方>
便利なAIですが、注意すべき点もあります。
特に使い始めの方は、以下の点を必ず意識してください。
まず、AIの出力結果は「叩き台」だということです。
情報が古かったり、事実と異なる内容が含まれていたりする可能性があります。
最終的な判断・決定は必ず人が行い、重要な情報は別途確認を取りましょう。
そして最も重要なのが、機密情報の取り扱いです。
社内の機密データや個人情報は絶対に入力しないでください。
実際に、うっかり顧客リストや社内資料をAIに送信してしまい、問題になったケースも報告されています。
AIは学習に使用される可能性があることを常に念頭に置いておきましょう。
また、AIに依存しすぎるのも危険です。
自分で考える力を維持しながら、AIを「思考の補助ツール」として活用するバランス感覚が大切です。
<デジタル時代の新しいスキル>
AIとの壁打ちは、これからのビジネスパーソンにとって必須のスキルになりそうです。
うまく使いこなせば、情報収集から分析、企画立案まで、一人でできることの範囲が格段に広がります。
次回以降も、私たちの仕事や生活に影響を与えるオンライン技術について、実践的な視点でお話ししていきます。
デジタル技術を味方につけて、より効率的で創造的な働き方を実現していきましょう。