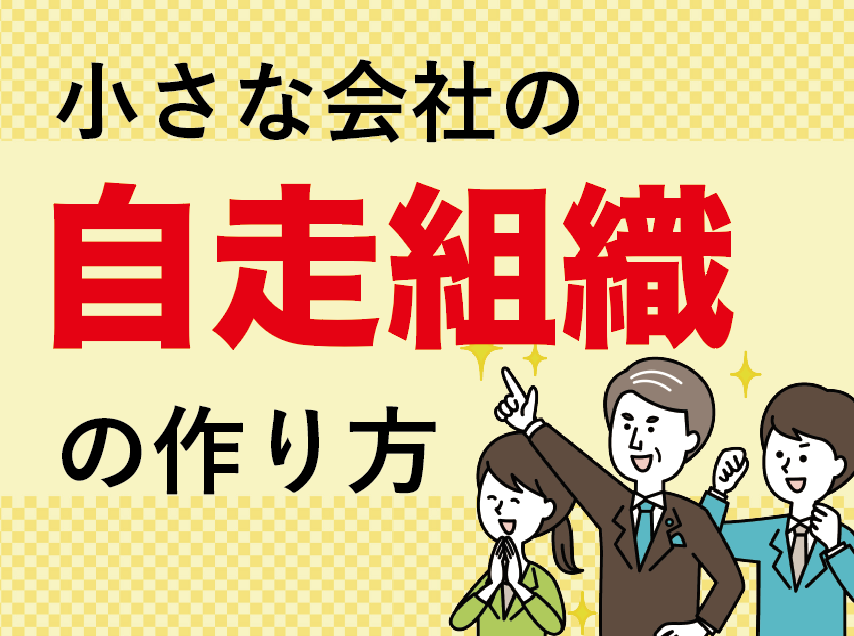第202回 「それ、教わってません」と言う部下に悩むリーダーへ
2025/03/17
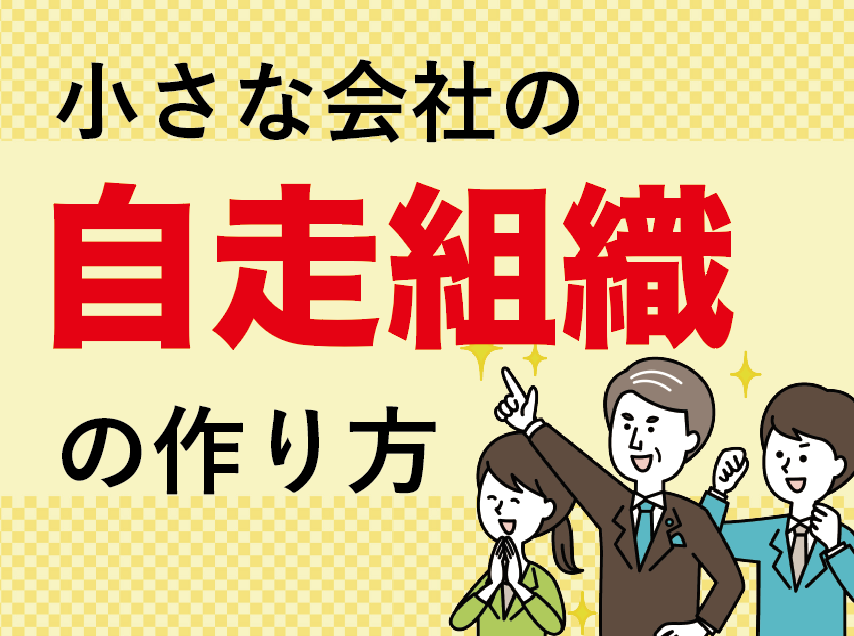
小さな会社では、一人ひとりが幅広い仕事をこなす必要があります。
しかし、そんな環境でリーダーを困らせるのが、すぐに「それ、教わってません」と言う部下です。
一見、正当な主張に聞こえるこのセリフ。
しかし、リーダーとしては、「教わっていないなら、自分で調べてみたのか?」「学ぶ姿勢はあるのか?」と疑問を持ちます。
このような部下にどう対応すればいいのでしょうか?
なぜ「教わってません」と言うのか?
まず、この言葉の背景にある心理はどうなっているのでしょうか?
①責任回避
「教わっていない」と言えば、自分の責任ではなくなると考えている。ミスをした際の保険のような意味合いで使うことがある。
②指示待ち体質
受け身の姿勢が染みついており、自分から考えて動く習慣がない。(教育の賜物!)
③失敗への恐れ
「間違えたくない」という不安から、何も手をつけずに「教わっていないからできない」と言ってしまう。
④会社の教育不足を指摘したい
「ちゃんと教えてくれない会社が悪い」という不満を持っている場合もある。
⑤完璧主義
「100%正しい方法を教わってから動きたい」と考え、自分で試してみる前にストップしてしまう。
「それ、教わってません」にどう対応するか?
では、このような部下にはどのように接すればいいのでしょうか?
効果的な対応策をいくつか紹介します。
①「教わってないなら、自分で調べてみた?」と問いかける
「教わってません」と言われたら、そのまま受け入れるのではなく、「じゃあ、自分で調べてみた?」と聞いてみましょう。
この質問に答えられない場合、受け身であることが明確になります。
ここで重要なのは、問い詰めるのではなく、「まずは自分で動く習慣をつけてもらう」こと。
調べ方のヒントを与えつつ、自主的な行動を促します。
例えば…
部下:「これ、教わってません。」
リーダー:「なるほど。じゃあ、まず自分で調べてみて、5分後にどうだったか教えてくれる?」
→ こうすることで、受け身ではなく能動的な姿勢を育てられます。
②「教わってない」を受け入れつつ、行動を促す
「確かに教えていなかったかもしれないね」と一旦受け入れると、部下も防御的にならずに話を聞きやすくなります。
そのうえで、「でも、こういう時はどうすればいいと思う?」と考えさせるのがポイント。
答えが出ない場合は、一緒に考える時間を設けることで、「自分で考える力」を鍛えます。
③「学ぶ姿勢」を明確な評価基準にする
「教わってません」と言う部下が増えないようにするためには、「自分で学ぶ姿勢」を評価基準の一つにすることが効果的です。
例えば、以下のような基準を設けます。
・自分で調べたうえで質問しているか?
・教えられたことをメモし、次に活かしているか?
・新しいことに前向きに取り組んでいるか?
これらを評価することで、部下も「受け身の姿勢では評価されない」と理解し、積極的に学ぶようになります。
まとめ
すぐに「それ、教わってません」と言う部下に対して、ただ叱るのではなく、どうすれば自分で考える習慣をつけられるかがポイントです。
1.「まずは調べてみた?」と問いかける
2.「教わってない」を受け入れつつ、行動を促す
3.学ぶ姿勢を評価基準にする
このような対応を続けることで、部下は少しずつ「自分で考える」ようになり、リーダーの負担も軽減されます。
さらに、内容はどうあれ「自分で考えた」「自分なりに調べた」と言う部分を評価することで、自発的なことがどんどん生まれる『風土』が育ちます!
「教わってないからできません」という思考から、「教わってないけど、自分でやってみよう」と思える部下に育てていきましょう!
『本の原稿』PDFでプレゼント中!
①『教育革命!小さな会社の自走組織作り方』(星寿美/プラウド出版)
②『こじれた関係 根本解決!』(星寿美/プラウド出版)
↓↓↓
ぜひ、参考にして大きな成果に繋げてくださいね!
※無料相談実施中!
自走組織育成実績73社。
後追い営業など一切なし!
困った社員・対立・組織運営などに課題を感じている方はぜひ1on1しましょう!