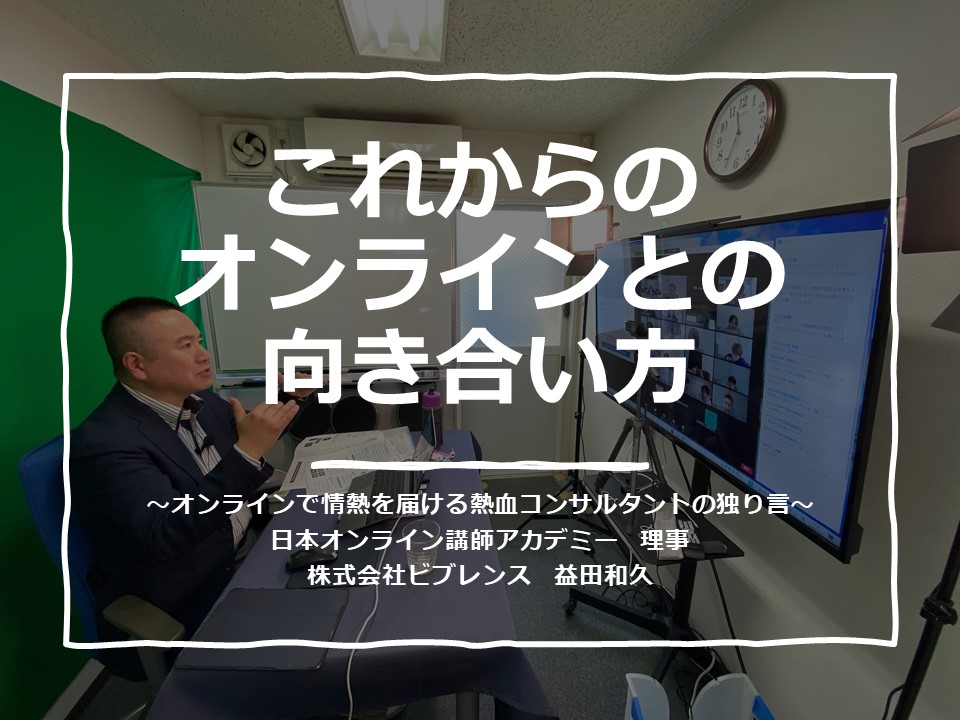医療用アプリ開発のスタートアップ企業が、飲酒量を減らすスマホアプリの製造販売承認を得たという報道がありました。
アルコール依存症の早期治療が狙いで、患者が医師の処方により当該アプリをダウンロードして使用します。
アプリで自身の飲酒習慣を記録することで、飲酒量を減らすためのアドバイスや飲酒のトリガーとなる状況を特定し、代替手段の提案をします。
国内では生涯でアルコール依存症患者は推計で107万人いるそうですが、専門的な治療を受けている人は約5万人にとどまるとのこと。
当該アプリを活用することで一般の内科でも専門治療に対応しやすくなり、専門治療が進むきっかけになることが期待されます。
このアプリは「飲酒量を減らすためのアドバイス」や「飲酒のトリガーとなる状況を特定し、代替手段の提案」とは、どのような内容なのか。
調べてみると以下のような内容でした。
<飲酒量を減らすためのアドバイス>
① 飲酒量の目標設定・・・毎週の飲酒量の目標を設定し、その達成状況を追跡します。
「今週は飲酒を3回までに抑えましょう」といった具体的な目標を提示します。
② 飲酒のタイミングと量の調整・・・特定の曜日や時間帯に飲酒を控えるように提案します。
「平日の夜は飲酒を控え、週末だけにしましょう」といったアドバイスです。
③ 自己監視とフィードバック・・・飲酒の記録を続けることで、進捗を確認し、自己評価を行います。
「今週は目標に近づいています。引き続き頑張りましょう」といったフィードバックを提供します。
何とか良くなりたいと思う人であれば、頑張れている自分を認識できるのは、励みになりますよね。
④ リマインダーと通知・・・飲酒を控えるためのリマインダーや通知を設定します。
「今日は飲酒を控える日です。代わりに新しい趣味を試してみましょう」といった通知を送ります。
飲酒に変わる新しい趣味を探すのは難しそうですが(苦笑)、飲酒を控えるリマインダーによって、量は減る可能性が高いです。
<飲酒のトリガーとなる状況を特定した代替手段の提案>
① ストレス解消・・・ストレス解消での飲酒はよくあるパターンです。
飲酒に頼らないストレス解消やリラクゼーション方法を提案します。
例えば、瞑想、深呼吸、ヨガ、散歩、軽い運動です。
瞑想やヨガ等でストレス解消ができるという実感がないと切り替われないと思いますので、まずはそれらを体感することが必要です。
② 社交的な場面・・・社交的な場面でアルコールに頼らない方法を見つけることですが、まずはノンアルコールドリンクを選ぶことになるでしょうか。
ビジネス上の懇親会や打ち上げも、乾杯だけビールにして後はウーロン茶にするのも一つですね。
③ 習慣的な飲酒・・・飲酒は意識、無意識関係なく「習慣行動」も多いかと思います。
のどごしを感じるための食前のビールを炭酸水に切り替えるとか、寝る前の一杯をストレッチに変えるとか。
これは180度急転換するとも思えないので、少しずつ回数を増やしていくしかないと思います。
そんなところですが、医師の処方と連動するアプリだけあり、レベルは高いと思いました。
具体的なアドバイスや代替手段の提示で自己管理は強化されると思います。
とはいえ、アプリの効果は個人の意欲や継続力に依存します。
また、アプリによるアドバイスが必ずしもすべてのユーザーに適しているわけではありません。
最終的には、個人の状況や目標に合わせた適切な設定を行うことが重要です。
アプリのアドバイスに従うだけでなく、専門家の助言もあるといいかもしれません。
いずれにしても、デジタルの力を活用するのは本人の「意思」。
あくまでデジタルの力は助言に過ぎません。
全てのデジタルツールに言えることですが、便利なものであるが故に、意図的(ねらいを持って)、継続的(結果が出るまでコツコツ続ける)な活用マインドを持つことが大事だと再確認した今日この頃です。