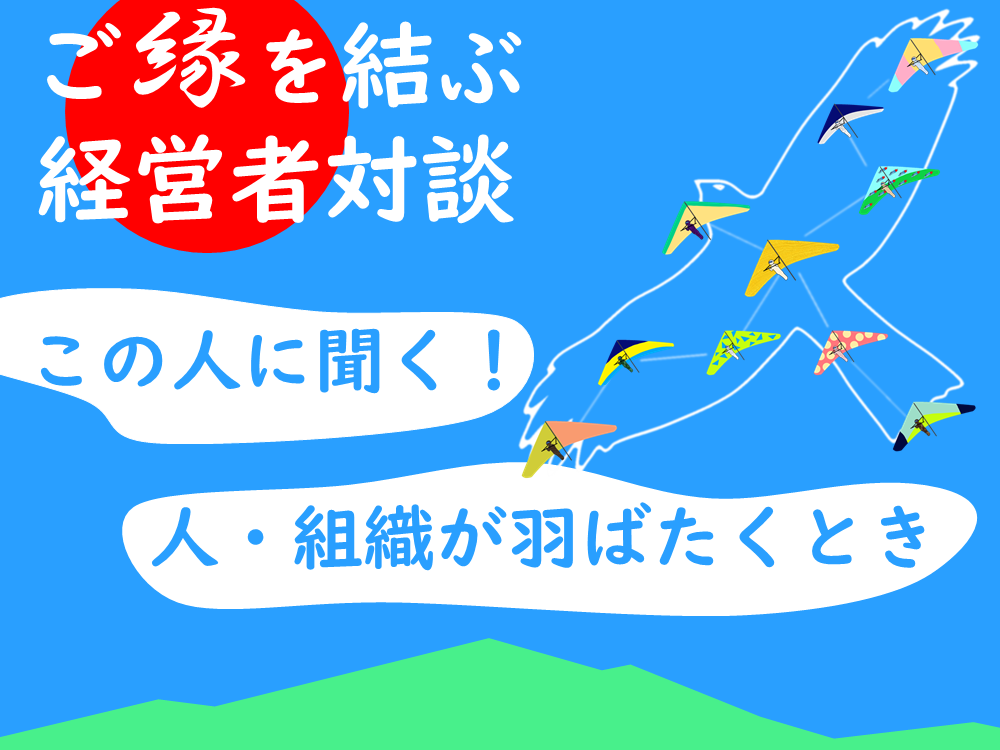株式会社サイバーテック 代表取締役社長 橋元 賢次様(其の2)

今回の対談は、株式会社サイバーテック代表取締役社長 橋元 賢次様にご協力頂きました。
株式会社サイバーテック様は「ITによる社会貢献」を理念に、マニュアルDX事業、Web CMS事業、開発・制作支援事業を展開されております。
今回は株式会社サイバーテック様の創業から現在までの歩みについてお話しを伺います。
金山:先週は主に会社紹介をして頂きましたが、創業の経緯や創業から現在までの歩みについてお話し聞かせて頂けますでしょうか。
半導体からWebの世界へ──インターネット黎明期が変えたキャリアの軌跡
最初は総合電機メーカーに新卒で入社しまして、半導体の設計をする部門に配属されました。
配属された部署では半分デバイスの設計、半分研究開発みたいなところで面白かったんですけれど、半導体なので、基本的に機器の中に入っているものなので、人目に触れるものでもなく、あまりやりがいを感じることができませんでしたね。
ちょうどその頃、インターネットが登場し始めたんです。
私が出会ったのは1996年か1997年くらいだったと思います。
当時は、まだ「Eメールって何?」というような時代でした。
ただ、私が所属していたのは、いわば研究所的な色合いのある部署で、比較的先進的で新しい技術を試せる環境だったんですね。
そんな中でインターネットに触れて、「これは面白い」と感じました。
今でこそご法度ですが、当時は副業として、Perlを使って色々な掲示板を作ったり、動的なウェブサイトや通常のウェブサイトを開発したりしていました。
そのうちに副業がどんどん面白くなっていって、気がつけば本業よりもそちらに比重が移っていった、という流れです。
金山:なるほど。
会社として設立をされたのはいつ頃になるのでしょうか。
創業当時のお話しを聞かせて頂けますでしょうか。
1998年、吉祥寺の一室から始まったIT起業のリアル
私が会社を設立したのは1998年9月のことです。
それまでは、今で言う「在宅ワーカー」のような形で仕事をしていました。
そんな折、以前勤めていた会社(八王子の高尾にありました)から少し都市寄りの吉祥寺にある地域プロバイダー(ISP)の運営者から、会員と設備一式を譲渡したい、という話を耳にしました。
確かメーリングリストか何かでその情報を知ったと思います。
話を聞きに行くと「これは面白そうだ」と感じ、引き継ぐことを決意しました。
それをきっかけに、親から借りたり、ためていた資金を使って当時の有限会社の最低資本金である300万円をかき集め、会社を立ち上げました。
そのお金はそのままプロバイダー事業の取得費用に充てられ、ほとんど資本のない状態からのスタートでした。
引き継いだプロバイダーには約200人の会員がおり、サーバーやモデムといった設備一式も含まれていました。
設備はデータセンターではなく、雑居ビルの一室に設置されていて、部屋ごと引き継ぐ形だったので、そこをそのままオフィスとして使いました。
そのおかげで、当時は珍しかった「常時接続の専用線」が独立当初から利用できたのも大きなポイントでした。
夜11時になると「テレホーダイ」というNTTの定額制使い放題サービスの時間帯に入るため、会員が一斉にアクセスし、自分はほとんど使えないという状況になりましたが、日中は回線も空いていて快適に使えました。
このプロバイダー事業が私の最初の事業となりましたが、もともとISPをやりたかったわけではありません。
引き継ぎを決めた理由は2つあります。
1つ目は、当時は個人で何かをしているというだけではなかなか信用されず、情報発信の手段も乏しかった時代。
地域でプロバイダーを運営していると言えば、それなりの信頼を得られると考えたからです。
2つ目は、プロバイダーの設備が手元にあり、そこで仕事をしながらネットワーク環境を活用できるという点。
当時としては、設立したばかりの会社で常時接続の専用線が使える環境は非常に珍しく、大きなアドバンテージでした。
会社設立の根底には「ITによる社会貢献」という理念があり、それは今でも変わっていません。自社で製品やサービスを開発・提供し、社会の役に立てるようなことをしたい、という思いから始まっています。
そのような思いから、ソフトウェアを受託開発するのではなく、自社製品を作り、CD-ROMなどの形で広く提供していました。
コストを分散できる点が魅力で、開発費をユーザーで分担するようなイメージです。
具体的には、LinuxベースでPostgreSQLをブラウザから管理できるツールや、メールマガジン配信エンジンのようなものを自社開発して提供していました。
今とは違い、XML系ではない技術を使ったものが中心でした。
金山:どのような経緯でXMLを中心とした事業にシフトしていかれたのでしょうか。
XMLとの出会いが導いた、製品ベンダーとしての道
当時はLinux技術を中心に深く関わっていましたが、あるきっかけでXMLに出会いました。
というのも、先ほどお話ししたPostgreSQLのようなRDBは柔軟性に乏しく、物足りなさを感じていたんです。
そんな中で、XMLというデータフォーマットに触れ、その柔軟性の高さに強く惹かれました。
ちょうどその頃、海外からXMLをベースにしたデータベースエンジンが持ち込まれてきて、「これはすごい」と感じたのが始まりでした。
Linuxという少し尖った領域にいたことで、「こういうことできますか?」というような技術的な相談が多く寄せられ、XMLを活用する機会も増えていきました。
その中でも特に印象的だったのが、当時「世界初の商用XMLデータベース」と言われていたeXcelonという製品との出会いです。
この製品を使った開発に取り組んだことで、本格的にXMLの世界へと踏み込んでいきました。
その分野にずっと関わり続けてきた中で、いろいろな出来事がありました。
話せば長くなるのですが、特に印象的だったのが eXcelon との関わりです。
eXcelon は当初、日本にも法人が設立されて販売されていたのですが、海外企業同士のM&A(合併・買収)が繰り返されたことで、プロダクトの方向性が混乱し、最終的には日本市場から撤退することになりました。
ただ、そのベンダーは別製品の販売は日本国内で実施する方針だったようで、撤退することで評判を落とさずに既存の製品サポートをどうするか、という話があったようです。
私たちの会社では、ちょうどそのタイミングでeXcelonを使った開発をガリガリ進めていたので、自然とその後の事業の引き継ぎに関する声がかかりました。
いくつかの企業とのコンペの末、最終的に我々がその製品事業を引き継ぐ形になり、事実上、eXcelonを買い取るような形でXMLデータベース製品事業をスタートさせました。
こうした経緯を経て、当社は完全に「製品ベンダー」という立ち位置にシフトしていき、現在に至るまで、主に文書管理やドキュメント関連の製品開発を中心に事業を展開しています。
金山:技術への深い探求心といいますか、理念としている「ITによる社会貢献」を追求し続けた結果生まれた出会いなんですね!次週は橋元さんが描くビジョンについてお話し聞かせてください。