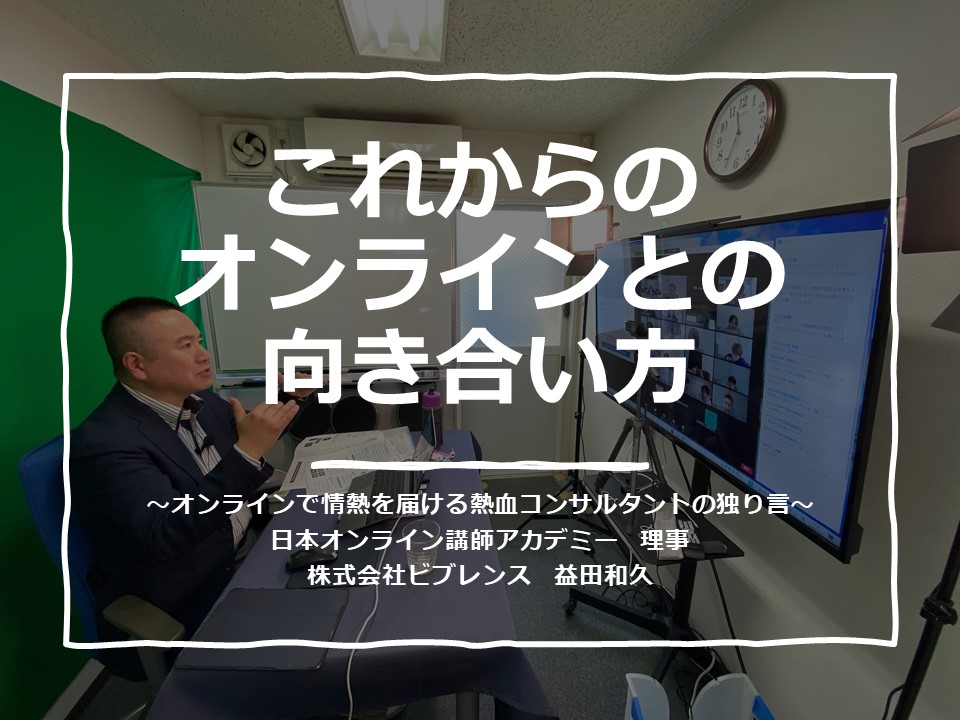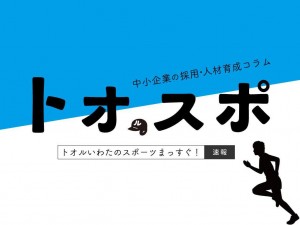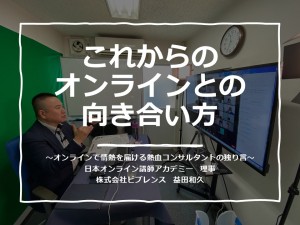故郷鹿児島で仕事が年に数回ありますが、ありがたいことに両親が健在ですので、宿泊や食事は実家の世話になることが多いです。
とはいえ、両親は2人とも80歳を超えており、年々着実に年老いていますので、今後は考えなくてはいけないなぁと感じているところです。
特に父は75歳を過ぎて耳が遠くなってきてからコミュニケーションが取りづらくなり、コロナ禍で外出しなくなってから、急激に衰えてきたような気がします。
父は今でも週に何度か畑仕事をしているくらいなので、日常生活にはさほど支障はありませんが、耳が遠いことによるコミュニケーションエラーが最大の問題。
3~4日滞在した私がストレスを感じるくらいなので、そばにいる母には想定以上にしんどいと思います。
うちの母は、学校教員でしたがかなり早い段階からPCを活用していましたし、携帯やスマホ、タブレットなども当初からよく使いこなしています。
息子などは小さい頃は「コンピューターおばあちゃん」と呼んでいたくらい。
そもそも本人が好奇心旺盛であり勉強家でもあるので、同世代の方と比較すると圧倒的にITリテラシーは高いと思います。
LINEがリリースされたときから私たちとのやりとりでは使っているし、ビデオ通話などは日常的に活用しており、鹿児島の両親とうちの家族全員で懇談していますから、遠く離れてはいますが、”距離感”のようなものは感じません。
そんな母と真逆で父は超アナログ。
IT関係、PC、スマホなどはサッパリ。
スマホは持ってはいますが、もっぱら受信専用。
電話はかけることがありますが、ガラケーで十分です。
以前よりデジタルコミュニケーションの便利さや、スマホ・タブレットでできることを、母や私がいろいろ伝えてきましたが、興味を示すことはありませんでした。
以前はそれでもよかったのかもしれませんが、耳が遠くなってきたり、体調が不安定だったり、忘れっぽくなってきたりすると、状況は変わってきます。
本人は何とも思っていないかもしれませんが、サポートする側からすると、自己完結を目指すならスマホ等のIT関連デバイスを上手に活用してほしいなと思うわけです。
例えば健康管理。
先週のウェアラブルウォッチの投稿でも書きましたが、今やスマホやウェアラブルウォッチは、健康状態の定点観測ツールとしては最強だと思います。
定期的に内科系病院も通っているようですから、先生もそのデータがあると、より適切な健康指導もできるでしょうし、サポートする母も助かると思います。
歩数計や心拍数モニターを活用して、マイペースでのウォーキングも楽しめます。
複数の薬も服用しているので、忘れないようにリマインダーアプリも活用できます。
予定は自宅リビングのカレンダーに書き込んでいますが、これもカレンダーアプリを使えばリマインドもしてくれるので、バタバタすることもなくなります(とはいえ、そこまで忙しいわけではないですが)
国語教員だった父は読書が大好き。
リタイア後に趣味でやっている農作業の畑は家から少し離れたところにあります。
一休みする小屋も作っており、まさに晴耕雨読を楽しんでいますが、Kindleがあれば書庫スペースも不要。(今は結構本が置いてあります)
本を読みながら、外付けスピーカーとかに接続すれば、父の好きな音楽をBGMにしながら読書も出来ます。
映画も好きなので、プロジェクターを買えば、小屋でミニシアターも楽しめるのになぁと父に話しましたが、「へぇ、そうなの」の素っ気ない一言(苦笑)
まぁ、長らく紙の本を愛してきた人に、趣味の畑に創った小屋での読書のひとときに、Kindleはイメージがつかないし、音を流すならラジオだろうし、映画は映画館で鑑賞するものなのでしょうね。
高齢者のデジタルライフへの転換は、そう簡単でもないし、時間もかかるということ。
今の70代後半から80代の人は、デジタルに巡り会うのが遅かったのかもしれません。
うちの母のように興味のある人でないと、なかなか適応も難しい。
今後の高齢化社会を考えるとデジタルツールのサポートは不可欠です。
そのためにも高齢者に対しては、デジタルツールの利便性や合理性を、あらゆる角度から訴求し、使わせるという方向に仕向けることが必要だと感じた帰省先でした。