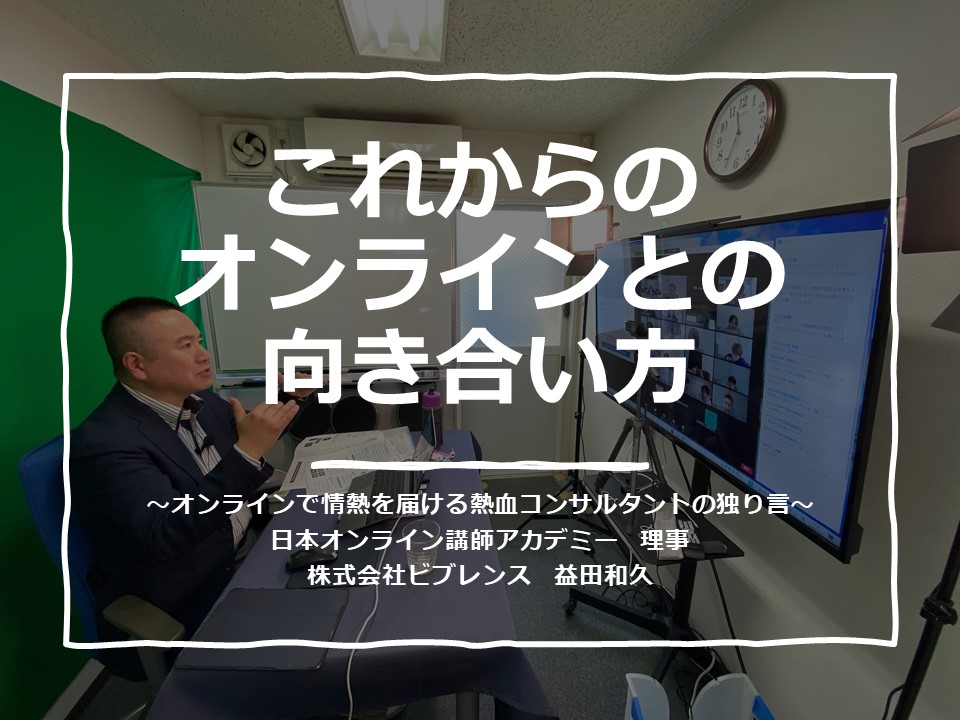先日、日本経済新聞にNTTデータと東京海上日動火災保険が介護と仕事の両立支援事業を始めるという記事が掲載されました。
人事教育コンサルタントとして、デジタル技術と人間の関わり方について日々考えている私にとって、この記事は単なるビジネスニュース以上の意味を持っていました。
なぜなら今年4月に母が亡くなり、87歳の父が鹿児島で一人暮らしになったことで、私自身が「ビジネスケアラー」の当事者となったからです。
父は比較的元気で、一人暮らしは順調にスタートしました。
しかし7月末になって持病が悪化し、入院することになりました。
2か月ほどで退院したものの、すぐに別の病気で再入院となり、現在も入院中です。
東京と鹿児島という物理的な距離がある中で、入退院の手続きや入院中のサポート、家主のいない家の管理など、想定をはるかに超える業務が発生しました。
一人っ子の私は、妻子のサポートを借りても限界があります。
そこで頼ったのが、様々な外部サービスでした。
家政婦サービス、セコムの見守りサービス、宅食サービス。
入院中には病院の勧めもあり介護申請を行い、退院後の介護体制も整えました。
知人の助言があったおかげで、すぐにこうしたサービスにたどり着けましたが、もし何も知らなければ、介護はもっと大変だったでしょう。
私のケースは、まだましな方だと思います。
今回、記事を読んで強く感じたのは、国のサポートだけでは不十分だということです。
記事にもあったように、民間企業や非営利団体が手掛ける外出支援や家事代行といったサービスは不可欠です。
これらのサービスには原則、介護保険が適用されず、料金も業者によって幅があり内容も様々だとのこと。
まさに私が実感したとおりです。
そうした中で、専門家が相談者と業者の間に入り、適切なサービスを探し出す手間を軽減してくれるというNTTデータの新会社のサービスは、非常に価値があると思います。
新会社「NTTデータライフデザイン」は、企業向けと個人向けの二つのサービスを提供するそうです。
企業向けには従業員の介護実態調査、セミナー、相談体制の整備など、個人向けには介護の専門家が回答するオンライン窓口を開設します。
これらの業務を効率化するシステムはクラウド経由で提供され、デジタルトランスフォーメーションが介護分野に広がる契機となります。
私自身、自営業なので休暇は自己判断で取得できますが、それでもそう頻繁に休めるわけではありません。
会社員であれば、介護休暇や介護休業といった制度があるものの、職場の理解を得るのが難しいケースも多いでしょう。
だからこそ、記事にあった「制度の周知を徹底し、制度を利用する人に対する職場の理解向上も狙う」という取り組みは重要です。
介護離職というのは、なるべくないようにしたほうがいいと、以前から思っていました。
しかし今回、自分がその境遇に近い状況になってみて、その思いはさらに強くなりました。
団塊世代が全員75歳以上となる「2025年問題」を迎え、働く人の介護負担は確実に高まっています。
経済産業省によると家族を介護する人は2030年に約833万人に達し、そのうちビジネスケアラーは約318万人と4割近くを占める見通しです。
一方で現状、多くの企業は従業員の介護実態を十分把握していないとのこと。
対策が行き届いていない企業では、介護の問題を個人で抱え込んでしまい孤立する懸念があります。
全産業的な人手不足が予想される中、介護離職による人材流出リスクも高まります。
企業にとって、ビジネスケアラー支援は単なる福利厚生ではなく、経営戦略の一部なのです。
NTTデータの新サービスの特徴は、ITを活用したデータ連携基盤の構築にあります。
オンライン窓口の利用データなどを蓄積し、匿名化したビッグデータとしてサービスの品質改善に活用するとのこと。
介護業界が情報セキュリティーや個人情報保護に配慮しながら、横断的にデータを利活用できる環境を整備することは、業界全体の発展にもつながるでしょう。
記事によると、ビジネスケアラーの支援事業は、ベネッセホールディングス系やパソナグループ系の企業なども手掛けているそうです。
後発のNTTデータがIT技術を武器に展開を広げ、東京海上日動の法人販路を活用しながら開拓を進める計画だとのこと。
30年度までに導入企業500社、個人会員30万人を獲得し、年間売上高100億円を目指すという目標は、この分野への期待の大きさを物語っています。
私が今回の経験を通じて特に感じたのは、こうしたサービスが大企業だけでなく、中小企業にも広がっていく必要があるということです。
むしろ中小企業こそ、一人の従業員が抜けた時の影響が大きいため、介護と仕事の両立支援が重要になります。
しかし中小企業には、独自に支援体制を整えるリソースがありません。
クラウド経由でサービスを提供するという今回のモデルは、中小企業でも導入しやすい仕組みだと思います。
もちろん、デジタル技術はあくまで手段です。
オンライン相談窓口があっても、そこに誠実に対応してくれる専門家がいなければ意味がありません。
記事にあるように、新会社が専門家を社員として雇用し、継続的に相談できる伴走型の支援体制を敷くという点は評価できます。
介護は一度相談して終わりではなく、状況が変化していく中で継続的なサポートが必要だからです。
デジタル化により、介護の情報格差も縮まっていくでしょう。
これまで知人のネットワークや地域のつながりがなければアクセスできなかった情報やサービスが、オンラインを通じて誰でも利用できるようになります。
ただし、それには高齢者を含めたデジタルリテラシーの向上が不可欠です。
前々回のコラムで触れた「東京スマホサポーター」のような取り組みが、ここでも重要になってきます。
介護と仕事の両立は、これからの日本社会が避けて通れない課題です。
デジタル技術を活用した支援サービスが広がることで、介護離職を防ぎ、働きながら家族を支えられる社会が実現することを期待します。
そして何より、当事者である私たち自身が、利用できるサービスを積極的に探し、遠慮なく助けを求める姿勢を持つことが大切です。
ビジネスケアラー支援を起点にしたデジタルトランスフォーメーションは、介護分野だけでなく、医療や福祉全体にも波及していくでしょう。
NTTデータの新会社の取り組みが成功し、介護と仕事の両立が当たり前にできる社会の実現に向けた一歩となることを、大いに期待したいと思う今日この頃です。