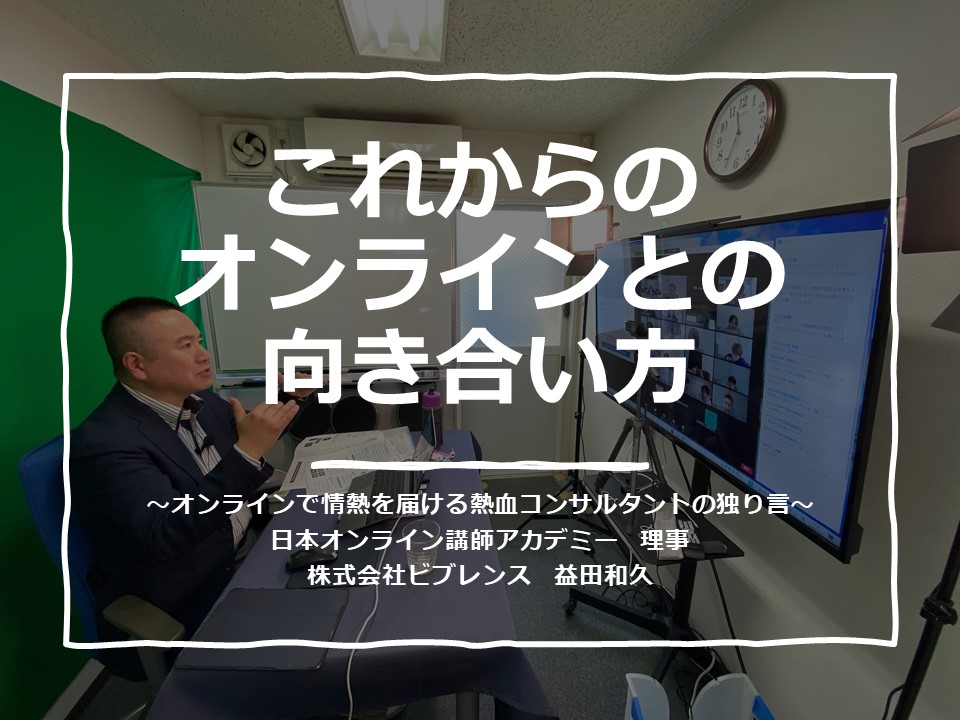日本経済新聞に「スマホ長く使うほど孤独感 若者は幸福感じる対面重視へ」という記事が掲載されていました。
記事によると、2024年の内閣府調査で「孤独を感じる」人の割合は、スマホ使用時間が1時間未満で35%、8時間以上では53%と、長時間使用するほど孤独感が高まる傾向があるとのことです。
理化学研究所の研究では、対面での会話が孤独感を減らし幸福感を増やす一方、SNSなど不特定多数とのオンライン交流は逆の効果をもたらすことが判明しました。
また、会社員の高橋遼さん(23)のように「1本くらいと見始めるといつの間にか2時間経っている」ショート動画依存や、デジタルデトックスイベントの広がりなど、現代人のスマホとの複雑な関係が浮き彫りになっています。
私自身は、この記事を読んで意外な印象を受けました。
というのも、研修の休憩中に他の参加者と会話をせずにスマホを見ている人が非常に多いからです。
特に若い人にその傾向が顕著で、同期や同部署などの話しやすい関係ができていると休憩中は雑談が中心になりますが、それ以外のスキル習得系研修や顔見知りが少ない組み合わせでは、やはりスマホを見ています。
昼休みも、一人でスマホを見ながらお弁当を食べている人が多いのが現実です。
彼らは後から「その時間が無駄だった、せっかく研修に来たのだから、他の人と会話すればよかった」と思っているのでしょうか。
それは何ともわかりませんが、もしそうなのならば、研修教室のルールとして、なるべく脱スマホになるような呼びかけをしてあげた方がいいのかもしれません。
記事にある「対面での会話が孤独感を減らし、幸福感を増やす」という研究結果を考えると、研修という貴重な学びの場での人間関係構築の機会を逃すのはもったいないと感じます。
記事では、20代の会社員が60秒程度のショート動画から離れられず、「1本くらいと見始めるといつの間にか2時間経っている」「また時間溶けた」と語るショート動画依存の話が紹介されています。
以前からよくあったネットサーフィンで時間が経過してしまう現象と本質的に同じだと思います。
私見ですが、あてもない情報収集、情報検索というのはそういった状況に陥りがちです。
時間をかけた割には、具体的なアウトプットがなかったということです。
採用支援のRECCOOの調査では、Z世代の約9割が毎日ショート動画を見るが、83%が「無駄な時間」と考えているとあります。
今回の記事は仕事というよりはプライベートや自己啓発の部分が多かったので、だらだらとSNS検索をするぐらいなら、もっと充実した時間を過ごしたいという心の表れだと思います。
実際、ショートではなく15分から20分くらいの動画だと、ためになるものがたくさんあります。
そもそもショート動画で何かを得ようということ自体が短絡的なのかもしれません。
それよりは友達とおしゃべりした方が、学びや気づきはたくさんあるような気がします。
また記事では、これも20代の会社員の方が、デジタルデトックスイベントを始めた話が紹介されています。
岡山県の離島への旅で「電波の届かない部屋で、3人でトランプをして他愛のないおしゃべりをしていると『いま、ここで生きている』という満足感が胸に染み渡った」というエピソードは印象的です。
このデジタルデトックスの流れは、とてもいいことではないでしょうか。
このコラムでも何度も書いていますが、ある意味強制的な環境にしないとデジタルデトックスはできないし、それに伴う自分自身の感性の磨きもできないような気がします。
AI活用が仕事で進んでいるので、仕事中の脱SNS・脱スマホは難しいと思いますが、プライベートこそ多くの人と対面交流をして、自然に触れて、直感で行動することで、いろんな気づきや学びがあるはずです。
記事にあるオランダの「オフライン・クラブ」が7カ国に広がったことや、日本デジタルデトックス協会の講座受講者が増加していることは、多くの人が同じ課題を感じている証拠でしょう。
人間力が高ければ高いほど、インターネットの活用は効果的になります。
前回も書きましたが、いかに自分をAIに引き上げてもらうかが大事です。 だからこそ、ネットに頼らない生身の自分を大切にすべきではないでしょうか。
記事で紹介された研究結果のように、対面での交流こそが本当の幸福感や充実感をもたらします。
つながっているようで孤独を感じる現代だからこそ、デジタルとアナログのバランスを見直し、リアルな人間関係の価値を再認識する時期に来ているのではと感じる今日この頃です。