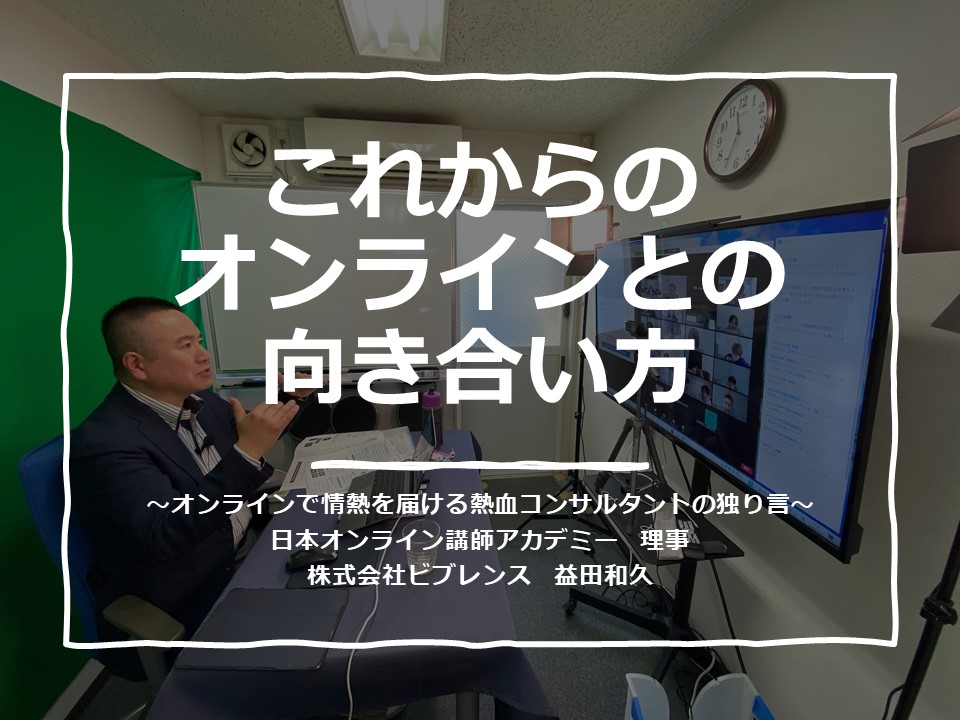コロナ禍以が降の新入社員研修において、受講者の方と話をしていると、情報収集の主な手段がSNSやニュースアプリである方が非常に多くなっていることを感じます。
情報源はもっぱら「yahooニュース」「Smart News」、さらには「X(旧Twitter)」や「TikTok」が中心の人もいます。
新聞を読んでいる人は少ないですね(いないと言っても過言ではない)。
何も情報収集をしていないよりは良いですし、関心のきっかけとしては悪くありません。
SNSやニュースアプリは、手軽さとスピード感が最大の利点です。
通勤中や休憩時間にパッと見られること、話題になっているトピックを短時間でチェックできる点は、日々の雑談やお客様との軽い会話においても一定の効果を発揮します。
実際、「昨日の地震、びっくりしましたね」や「政治家の○○さん、最近また炎上してましたね」といった話題は、SNS由来のネタで場が和むことも多いでしょう。
しかし、SNSに頼りすぎた情報収集には注意が必要です。
アルゴリズムによって興味のある記事ばかりが表示され、似たような意見や視点の情報ばかりが流れてくる「フィルターバブル」や「エコーチェンバー現象」が起きやすく、結果として情報が偏ってしまいます。
また、記事の内容も見出しや要約レベルのものが多く、背景や本質的な解説が十分になされていないことがほとんどです。
新聞に掲載されている情報の10%にも満たない浅い理解にとどまっているケースもあるでしょう。
例えば、ある新入社員が「半導体不足で業界が混乱しているらしいですね」と話していたとします。
しかし、「なぜ不足しているのか」「どういった企業や国が影響を受けているのか」「今後どうなる見通しなのか」といった深掘りには至っていないことが多く、知識としては表面的です。こうした局所的な理解しかないと、ビジネスの現場で議論に加わるのが難しくなり、判断力や提案力に影響してしまいます。
そこで推奨したいのがやはり、「新聞を読む(触れる)習慣」です。購入しなくても会社に置いてあるものを読んでもいいし、今や新聞は「速報性」という観点では最も遅い媒体ですね。
しかし、その分、記者が裏付けをとり、専門家の視点を取り入れた丁寧な取材がなされており、一つひとつの記事に深みと信頼性があります。
さらに、政治・経済・国際・文化・スポーツなど多様な分野が網羅されているため、自分の興味・専門に偏らずに世の中を立体的に捉えることができます。
また、最近では、識者や専門家が読者コメントとして意見を述べる機能を備えた有料ニュースアプリも登場しています。
特に実名で議論が交わされるものは、コメント欄にこそ読み応えがあり、自分では思いつかなかった視点を得ることもできます。
無料版と違って一定の質が保たれており、学びとしても非常に有益です。
もちろん、SNSを完全に否定するつもりはありません。
大切なのは、「SNSをどう使いこなすか」です。
話題の入口としてはSNSやアプリを活用しつつ、深掘りは新聞や信頼できるメディアに切り替える。
あるいは、1つの記事に対して複数の情報源から裏を取る習慣を持つ。
その積み重ねが、自分の視野を広げ、考察の質を高めることにつながります。
ビジネスパーソンの情報収集力とは、単に「知っているかどうか」ではなく、「なぜそうなのか」「それが何に影響するのか」といった構造や背景まで理解しているかが問われます。
その力を養うためには、アプリの使い方だけでなく、何のために情報を集めるのかという目的意識が不可欠です。
SNSは「使うもの」であり、「使われるもの」ではありません。
情報の波に流されるのではなく、選び、深め、活かす。
その姿勢が、これからのビジネスパーソンには求められています。
少しずつトライしてみてください。