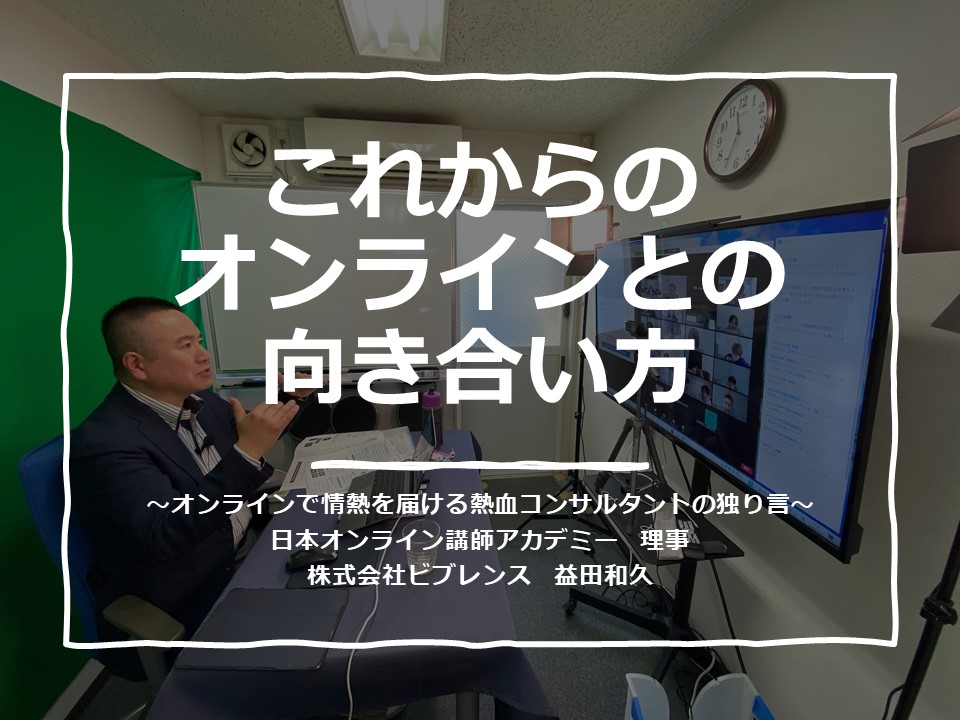前回は、「ググる」よりも「コパる」ことの合理性、効率性の良さを書きました。 前回の文末で「次回は『コパる』ことのデメリット」に言及すると書きましたが、その前にもう少しだけ「コパる」ことのメリットや生活上の変化を考えてみたいと思います。
情報検索をするときに、「ググる」より「コパる」ことが当たり前になってくると思いますが、企業や団体が「ChatGPT」を業務に導入することもごく当たり前になってくるでしょう。
そうすると働き方も確実に変わるはずです。
真っ先に考えられるのは、新入社員とベテラン社員のノウハウや経験の差がなくなることです。
営業や販売は顕著かもしれません。
商談のときにお客様から「このAというシステムを導入すると弊社の規模だとどれくらいの効果がありますか?」「Bというシステムは、〇〇〇〇のような不具合が生じる場合が想定されますが、これはどのように対応するのでしょうか?」等の問い合わせを受けたとしましょう。
営業場面ではよくある話です。
これまでは経験や知見がないと、「すぐに調べてご連絡します」「いったん持ち帰って上司に相談します」とお詫びをして自社に持ち帰り、上司や先輩の判断や指示を仰ぐというのがお決まりだったと思いますし、現在もそんな感じですね。
それが、社内に「ChatGPT」が導入されるとどう変わるか。
あくまでも導入したChatGPTが、社内情報を確実に学習したということを前提で想像してみました。
前出の質問「このAというシステムを導入すると弊社(客先)の規模だとどれくらいの効果がありますか?」は、その場で商品名と一定のお客様情報を入力すると、チャット形式で回答を得ることができます。
更には「御社のような従業員数100名という規模でしたらAというシステムはメリットがありますが、少し安価なBというシステムにはメリットがありません」といったことまで説明してくれると思います。
その回答を踏まえたお客様からの質問を想定して「では現時点での前提条件から、弊社(客先)にとって、最適なシステムはどれでしょうか?」と所定の前提条件を入力すれば、「Gというシステムをおすすめします」という回答が、Gというシステムの詳細や効果とともに表示されるでしょう。
現状の「いったん持ち帰って上司に相談します」という対応と比較すれば、お客様の意思決定(購買意思)を速やかに確認ができ、成約率は高くなると思います。
購買意欲が薄さやお断りもその場で判断できますので、営業活動は着実にスピードアップするでしょう。
こうなってくると、ベテラン社員が培ってきた経験や知見は、内容によってはあまり価値のないものになりますし、自業務を進める上で必要な知識や情報が少なくても、ChatGPTでそのハンディをカバーすることは可能です。
ではこれからどういったスキルやリテラシーで勝負(差別化)をしていくようになるのか。
それこそ人間力やパーソナリティー、性格といったところが大きな割合を占めてくるのではないかと思います。
業種や職種にもよると思いますが、これからの働き方を想像しながら、AIとの共生を前提としたキャリアデザインを、考察・啓蒙していく必要性を感じた今日この頃です。